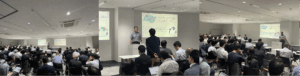2025/07/25
開催報告
CReM TONOHANE×RINKパネルディスカッションがRINK会員・記念イベントで開かれました。
2025年7月24日(木)、ライフイノベーションセンター(LIC)にて開催された2025年度RINK会員総会・記念イベントの第Ⅲ部として、当拠点主催・RINK共催のパネルディスカッションが開かれました。
第Ⅰ部、第Ⅱ部そして懇親会の詳細につきましては、かながわ再生・細胞医療産業化ネットワーク(RINK)のホームページ、こちらよりご覧ください。
【開催概要】
国立医薬品食品衛生研究所 副所長の佐藤 陽治氏よりパネルディスカッションの開催趣旨、そして当拠点の取り組みについて説明されました。
共同研究・連携体制の強化を向けて、 当拠点の参画機関のみならず、殿町・羽田エリアに属する研究者・医師ならびに企業の方より、 ご自身の研究(熱意、悩み、展望)を、
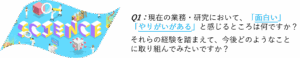
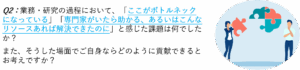
上記2問に対して、それぞれ普段の業務・研究過程で感じたことを率直に話されました。
藤田医科大学東京先端医療研究センター教授&神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)有望シーズ展開事業プロジェクトリーダーの遠山 周吾氏より、基礎研究から実臨床への橋渡しにおける課題、そして自身の研究領域から心臓オルガノイドによる新規治療法の開発等についても話されました。一方で、再生医療の原材料細胞そして細胞株の規格設計、製造プロセスの開発はアカデミアにとって限界を感じる場面が多く、こういった専門性の高い領域は企業と連携しながら進められたらと感じております。
慶應義塾大学医学部整形外科学教室専任講師の名越 慈人氏より、iPSC及びリハビリテーションによる一部脊髄損傷患者への治療結果から、確かな機能回復を観察できたことで、今後さらに安全性・有効性が担保された再生医療治療を開発し、脊髄損傷患者にはいち早く最新治療法の恩恵を享受できることを目指したいと話されました。しかし、臨床試験の実施は莫大なコスト(人的資源、資金、時間)を要し、最新技術(人工知能等)によって一部カバーできないか、今後、その可能性について検討したいそうです。
慶應義塾大学再生医療リサーチセンター(KRM)/殿町先端研究教育連携スクエア特任講師の児崎 達哉氏より、KRMにおけるラボの共同研究体制、iPSC細胞由来ミクログリアによる神経変性疾患における病態発症の解明、治療法開発について紹介されましたが、外部との共同研究の機会の少なさ、そして研究者同士の交流の場の欠如を指摘しました。
国立医薬品食品衛生研究所再生・細胞医療製品部第1室 室長の三浦 巧氏より、原材料細胞の不均一性に対する評価法開発、そして再生医療等製品等が開発時に直面する製法変更による有効性・安全性の担保等について、国立医薬品食品衛生研究所の役割そして自身の業務内容について語られました。しかしながら、新規モダリティの発現や新規評価法開発・標準化するために、多くのリソース(人的資源、資金、時間)を費やす必要があり、これら全てを日常業務で確保するには至難の業とコメントいたしました。
ロート製薬株式会社再生医療事業開発部臨床研究グループ東京臨床チームリーダーの近藤 光氏より、企業の立場から自身の薬剤師のバックグラウンドから再生医療等製品の開発における課題に対して、ロート製薬での再生医療に関する取り組みについて紹介されました。同時に、現段階では、再生医療等製品の承認は少数例による条件付き期限承認のため、臨床試験の規模拡大やスケールアップするための開発に要するコストが甚大で、製薬の観点からコスト削減が今後の開発効率に影響を与えるキーファクターとなると考えられます。
座長の佐藤氏による進行のもと、登壇者同士の議論のみならず、参加者からも多くの質問を寄せられ、活気に溢れたパネルディスカッションとなりました。